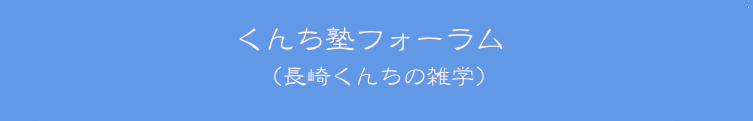賑町
賑町(にぎわいまち)
昭和38年の町界町名変更で材木町、今下町の全部と周囲の町の一部を合併して新しく誕生した町。
町名は、傍に賑橋があり、町が賑やかになって発展する様にと名付けられた。
ちなみに、「賑橋」は材木町と榎津町の間に架けられていて、その名前は材木のキと榎津のキが合う「2キあい」に掛けてつけられた。
傘 鉾
<飾>
波頭の波模様の台上に八足・八稜境を象る置台を配し、台上に海彦・山彦の神話に由縁の満珠(吹き玉技法のビードロ)を頂く。
<輪>
ビロードに金糸で町名。
<垂>
金銀の青海波。
奉納踊
「大漁万祝恵美須船」(たいりょうまいわいえびすぶね)
昭和40年 唐獅子踊
昭和47年 本踊「長唄 花櫻菊絵姿(はなざくらきくのえすがた)」
昭和54年 本踊「長唄 舞姿賑集諏訪御社(まいすがたにぎわいつどうすわのみやしろ)
昭和61年 恵美須船
平成6年 大漁万祝 恵美須船
平成13年 大漁万祝 恵美須船
平成20年 大漁万祝 恵美須船
平成27年 大漁万祝 恵美須船
奉納踊概要
昔、材木町(現賑町の内)に魚市場があった頃、中島川沿いに恵美須神社が祀られていました。今も大切にお祀りされております。
昭和61年の踊町の時、何か変わった奉納をしたいと思いたち、賑町に所縁の恵美須神社に因み「海の漁」をテーマにした「恵美須船」を奉納する事に決定した。
踊町の奉納踊の曳物には、川の漁をする「川船」、海の船としては、貿易船、御座船、龍船などがありますが、「海の漁」をする船は長崎くんちの奉納踊の中では唯一の物です。
<構成>
「恵美須船」「宝恵舟」「豊来舟」
<はやし>
[鳴物]
大太鼓・銅鑼・大鉦・小鉦・舟太鼓
[リズム]
大波、立波、小波の四小節を一フレーズとして、波のリズムを繰り返す。
<諸役>
船頭・長采・副采(4名)・根曳(20名)・若根曳(男女8名、計16名)囃子方(6名)・舟太鼓(4名)・舟采(4名)網方(20名)・波采(4名) 総勢80名
参照
踊町
賑町恵美須船(外部リンク:blog)
賑町恵美須船(外部リンク:Facebook)
編集者( )
このページは賑町に関する書きかけ原稿です。