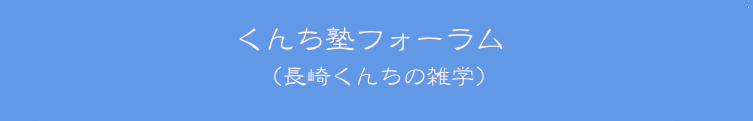上町
上町(うわまち)
昭和38年に東中町の全部と小川町、八百屋町、内中町、東上町の各一部を合併して出来た町。
傘鉾
<飾>
白木の八足の上に烏帽子、鈴、諏訪社由緒、後ろに榊と御幣。
<垂>
正絹本緞子(どんす)五色唐草模様に三社紋を金糸にて刺繍。
奉納踊
「コッコデショ」
平成21年度(2009)までは「本踊」を奉納していたが、
平成28年度(2016)からは「コッコデショ」を奉納。
永島正一氏は、上町(東中町)を以下のように紹介しています。
<東中町>
今は上町(うわまち)の内、西勝寺のある通り、昔唐津藩の屋敷もこの町にあった。
この町の傘鉾は榊(さかき)二株に、中央に金色の田楽(でんがく)を立て、それに町名、輪はシメ飾りで、たれは水色塩瀬地に金糸で三社紋。
出し物はバラエティーに富んで、いろいろ。明治三十五年に本踊り「常盤塚」、牛若丸と熊坂長範の芝居があると、その次の明治四十二年には「聯隊訓練」と題して、「江戸町の兵隊さん」のような出し物になる。歩兵の小銃発射、砲兵の大砲発射という勇壮は軍国調。聯隊長以下の将校、歩兵に砲兵、看護婦。歩兵は「道は六百八十里…」と歌い、看護婦は「小砲(こづつ)の響き遠ざかる…」と歌う。ラッパ手ももちろんいた。
次の大正六年になると目先ガラリと変わって、「鎧武者少年剣舞」となる。かと思えば大正十三年は、本踊りに戻って、前日「勢曽我」、後日「候良三国訛」となる。
昭和六年は剣舞。戦後昭和二十七年には、剣舞に少年鼓笛隊がついてピー、ヒャララの明治維新行進曲、馬上豊かにヨロイ姿の隊長が采配を振るという趣向。
常に目先を変えて新演出、誠に面白い踊り町である。
(昭和53年長崎新聞「くんち長崎」より)
越中哲也氏は、上町を以下のように紹介しています。
<上町>
この町の町名は、旧長崎の船つき場・船津町よりみて、上の通りにあるという意味で上町といい、その下の通り中町といった。そしてこの両町は、非常に長い通りの町であったので、両町とも、中央でわけて、東上町、西上町、東中町、西中町とした。
東上町、東中町の町筋の正面は共に、厳めしい、立山奉行所に面していたので、町筋はいつも整然と清められていた。
現在の上町は、その東中町を中心にして、旧小川町、八百屋町、東上町、内中町の四ヶ町の各一部が統合して構成されている。
傘鉾は旧東上町のものが使用され、榊を中心にして、その前に八ッ脚をすえ、烏帽子、鈴を配し、その下に、諏訪社縁起を配した、古式ゆたかな傘鉾である。
奉納踊りは本踊りをだしている。
(昭和62年長崎フォトサービス「長崎くんち」より)
参照
上町自治会コッコデショ(外部リンク)
長崎上町(外部リンク:Facebook)
長崎上町コッコデショ(外部リンク:Twitter)
踊町
編集者( )
このページは上町に関する書きかけ原稿です。